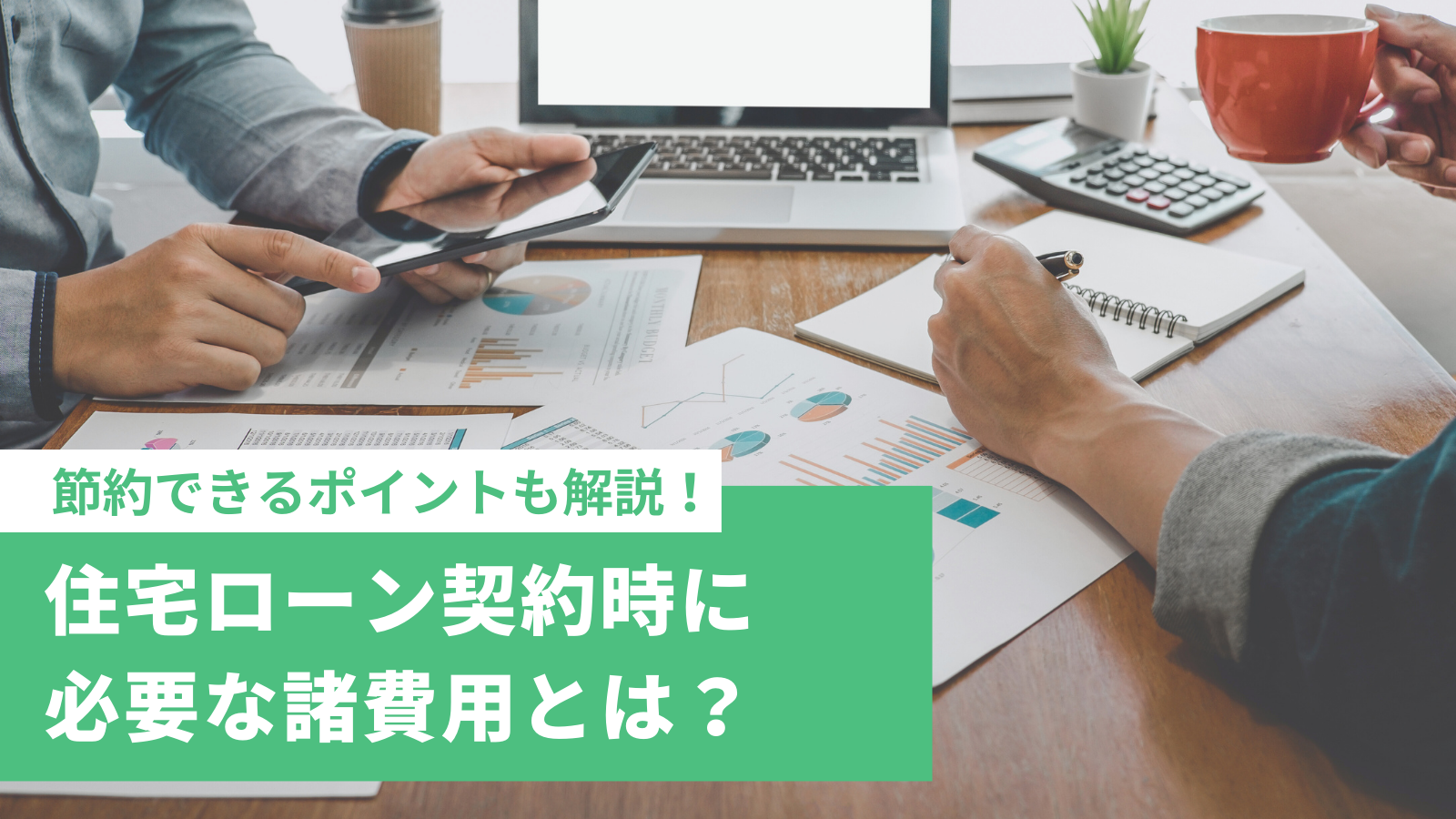住宅ローンを契約する際は、さまざまな諸費用がかかります。どのような諸費用がかかるかを知っておくことで、余裕を持ってお金を準備できるでしょう。
今回の記事では、住宅ローン契約の際に必要となる諸費用と目安の金額、諸費用が必要となるタイミングなどについて詳しく解説します。
諸費用を安く抑えるためのポイントについても紹介しているので、これから住宅ローンの借り入れを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
なお、現在すでに住宅ローンを借りている方が借り換えを行う際も諸費用は必要となります。ただし、諸費用を踏まえた上でも借り換えを行った方が、返済総額を減らせる場合があります。
借り換えのメリットについて詳しく知りたい方は、借り換えガイドもチェックしてみてください。
目次
住宅ローン契約時の諸費用一覧と目安金額
住宅ローンを組むためには、建物や土地代の他にも諸費用がかかります。
まずは、どのような諸費用がかかるか、どのくらいの金額がかかるのか、などについてチェックしていきましょう。
事務手数料
住宅ローンの事務手数料は、ローンを契約する金融機関に対して手続きの費用として支払うお金のことです。金融機関によって呼び方はさまざまで「事務取扱手数料」「融資事務手数料」「融資手数料」などと呼ばれることもあります。
事務手数料は、大きく分けると「定額型」と「定率型」の2種類に分けられます。
定額型の事務手数料は、借入金額にかかわらず一定の金額を契約時に支払います。借入金額が2,000万円でも5,000万円でも手数料の金額は一定です。そのため、借入金額が大きい人にとってはお得に感じられるものの、借入金額が少額の人にとっては割高に感じられてしまうかもしれません。
一方、定率型の事務手数料は、借入金額に対して一定料率をかけることで手数料の金額を算出します。「借入金額×○%」で金額が計算されるのが一般的なので、借入残高が大きくなるほど手数料も高くなります。定率型を採用している金融機関が多く、手数料の金額は「借入金額×2.2%」と設定されているのが一般的です。
保証料
住宅ローンの保証料は、保証契約の締結のために保証会社に対して支払う費用のことです。保証契約を結んでおけば、万が一住宅ローンの契約者が債務を返済できない状況に陥った場合に代位弁済を行ってくれます。ただし、保証会社が債務を代わりに支払ってくれたとしても、債務そのものがなくなるわけではなりません。債権者が金融機関から保証会社に変わるため、契約者は保証会社に対して残債を支払う義務がある点に注意しましょう。
保証料の金額は各金融機関が独自に設定していますが、支払い方法によっても、保証料の金額が変動します。保証料の支払い方法は「一括払い型」と「金利上乗せ型」の2種類です。一括払い型では契約時にまとめて保証料を支払いますが、金利上乗せ型の場合は毎月の返済額に保証料を含めて支払うこととなるため、借入金額や返済期間が大きいほど保証料の金額も上がります。
加えて、金融機関によっては、事務手数料が安くても保証料が高額に設定されているケースがあるため注意しましょう。逆に、ネット銀行などでは保証料がかからない場合が多いです。住宅ローンを比較する際は、手数料+保証料の金額で比べるようにしましょう。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書・手形などの取引に関する文書に課される税金のことを指します。文書に対してかかる印紙税は印紙税法によって金額が決められており、定められた金額に対応する収入印紙を文書に貼付することで、納付の証明とします。
住宅ローンの借り入れは「金銭消費貸借契約」となり、以下の金額に応じた印紙税が必要となります。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
例えば、住宅ローンとして3,000万円を借り入れた場合は、印紙税として2万円が必要となります。
登記関連費用
住宅ローンの契約時には、不動産登記に関する費用も必要となります。
そもそも登記とは、土地や建物などの権利関係を登記簿に記載することです。住宅ローンを組む際は、土地や建物が自分のものであることを証明するための所有権の登記とともに、抵当権の設定も行います。
抵当権設定は、基本的に司法書士が代行してくれることとなるため、登録免許税や登記代行手数料といった費用が必要です。
住宅ローンの抵当権設定にかかる登録免許税は、住宅ローンで借り入れた金額に0.4%をかけて算出します。仮に、3,000万円のローンを借りた場合は、3,000万円×0.4%=12万円が登録免許税として支払います。
司法書士に代行してもらうための登記代行手数料は、担当する司法書士によっても異なりますが、10万円前後が目安となるようです。
火災保険料
住宅ローンを組む際は、火災保険への加入が義務付けられるのが一般的です。火災保険は損害保険の一つで、火災や風水害、落雷などによる建物および家財の損害を保証するための保険です。
火災保険の保険料は保険のプランによって異なりますが、15万円〜50万円ほどが目安となります。木造一戸建てなど燃えやすい構造であるほど保険料が高く、鉄筋コンクリートのマンションなど燃えにくい構造であるほど安く設定されます。
なお、火災保険では、地震が原因となる損害については対象外となる点に注意が必要です。地震による津波や土砂崩れなどが原因で、倒壊や火災といった損害が発生しても、火災保険だけでは補償を受けられません。地震のリスクに備えたい場合は、火災保険と併せて地震保険にも加入する必要があります。地震保険料の金額は、地域や建物の構造によって異なります。
団体信用生命保険料
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、残りのローンを保険金で支払うという仕組みの保険です。住宅ローンの返済期間中に契約者に万が一のことがあったとしても、家族は残りのローンの心配をせずに生活を続けられるというメリットがあります。
団信の契約範囲は、金融機関や加入プランによってさまざまです。特約付きの団信を選ぶことで、3大疾病や要介護状態にも備えられるなど保障内容を充実させられます。
団信の保険料は、一般的に住宅ローンの金利に含まれています。特約を付加する場合は、0.1%〜0.3%程度の金利が住宅ローンの金利に上乗せされます。
諸費用を支払うタイミングについて
住宅ローンの諸費用を支払うタイミングは、一般的に以下の通りとなります。
| 諸費用の種類 | 支払うタイミング |
|---|---|
| 事務手数料 | 融資実行時 |
| 保証料 | 融資実行時または毎月の返済時 |
| 印紙税 | 契約時または融資実行時 |
| 登記関連費用(登録免許税、司法書士報酬) | 残金決済・物件の引き渡し時 |
| 火災保険料 | 物件が引き渡されるまでに |
| 団体信用生命保険料 | 毎月の返済時 |
諸費用の種類や金融機関などによって支払うタイミングが異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
諸費用を住宅ローンに組み込むことについて
ここまで説明した通り、住宅ローンを借りる際は、さまざまな諸費用が必要です。場合によっては100万円以上の諸経費が必要となるケースもあり、手元の資金では用意するのが難しいという方もいるでしょう。もしこれらの費用をすぐに準備できない場合、諸費用を住宅ローンに組み込むこともできます。
ただし、総返済額が増えてしまうことや、住宅の売却後もローンが残りやすくなってしまうことには注意しましょう。
住宅ローンの借り入れに組み込み出来ない費用
住宅ローンの中に含めて借りられる諸費用は、金融機関や住宅ローン商品によって異なります。
保証料や事務手数料、登記関連費用は住宅ローンに組み入れられるケースが多いですが、家具や家電等に関しては注意が必要です。
例えば、備え付けの家具や照明器具など住宅の工事代金に含まれる費用については、住宅ローンに組み込める可能性があります。しかし、一般的な家具や家電などの購入費用は、住宅購入に直接関係のない費用となるため対象外となります。
諸費用も住宅ローンに組み入れたいと考えている場合は、あらかじめどのような費用を組み込めるかを金融機関に確認しましょう。
住宅ローン諸費用を安く抑えるためのポイント
住宅ローン諸費用の金額は、金融機関や借入金額などによって異なりますが、100万円を超えることも珍しくありません。
なるべく諸費用を抑えたいと考えている方は、以下のポイントに注意しましょう。
事務手数料に注意しよう
住宅ローンの諸費用を安く抑えたいなら、事務手数料に注意しましょう。
金融機関や住宅ローン商品によって金額が異なる場合があるので、複数の金融機関を比較することをおすすめします。
ただし、事務手数料をチェックする際は、保証料も含めたトータルの費用を確認することが重要です。事務手数料が安く抑えられる金融機関の場合、保証料の負担が大きくなるケースがあります。特に、メガバンクでは事務手数料が安い代わりに保証料が高い傾向があり、ネット銀行では保証料が無料で事務手数料が高い傾向があります。
印紙税が不要になる電子契約を利用できるか?
書面による契約手続きには、契約金額に応じた収入印紙が必要です。しかし、電子契約を行った場合、印紙税は不要となります。印紙税の負担を抑えたいという方は、電子契約を検討してみましょう。
ただし、電子契約を利用するためには、一般的に別途手数料が必要となります。電子契約の利用料は金融機関によって異なるため、借入先の金融機関で確認してみましょう。
金利条件合わせた比較検討が大事
住宅ローンを契約する際は、事務手数料や保証料、保険料などさまざまな諸費用がかかります。どれか一つの項目を比べるのではなくトータルのコストを比較することが重要です。
一見、手数料負担は大きいように見えても、適用金利が安いことで総支払額は安く抑えられるケースもあります。
住宅ローンを組む際は、金利や団信の保障範囲、諸費用の金額などさまざまな条件を加味した上で、実際にどのくらいのコストがかかるのかをシミュレーションしてみることをおすすめします。
まとめ
住宅ローンを契約する際は、金利だけでなく諸費用もかかってくるため、どのくらいトータルコストがかかるのかチェックしておきましょう。住宅ローンの諸費用を安く抑えたい場合は、事務手数料や保証料をしっかりと比較した上で、電子契約を検討するのがおすすめです。ただし、金融機関の比較の際は、諸費用だけでなく金利や団信の保障範囲など、その他の内容についても考慮した上で借入先を選びましょう。
また、住宅ローンを借り換える際も、本記事で紹介した諸費用はかかります。そのため、住宅ローンの借り換えを検討する場合、諸費用も含めてどのくらい返済負担を抑えられるかが重要です。
「住宅ローンを借り換えたい」「借り換えによってどのくらい返済負担を抑えられるか知りたい」と考えている方は、ぜひ借り換えシミュレーションで、具体的なシミュレーションを行ってみてください。