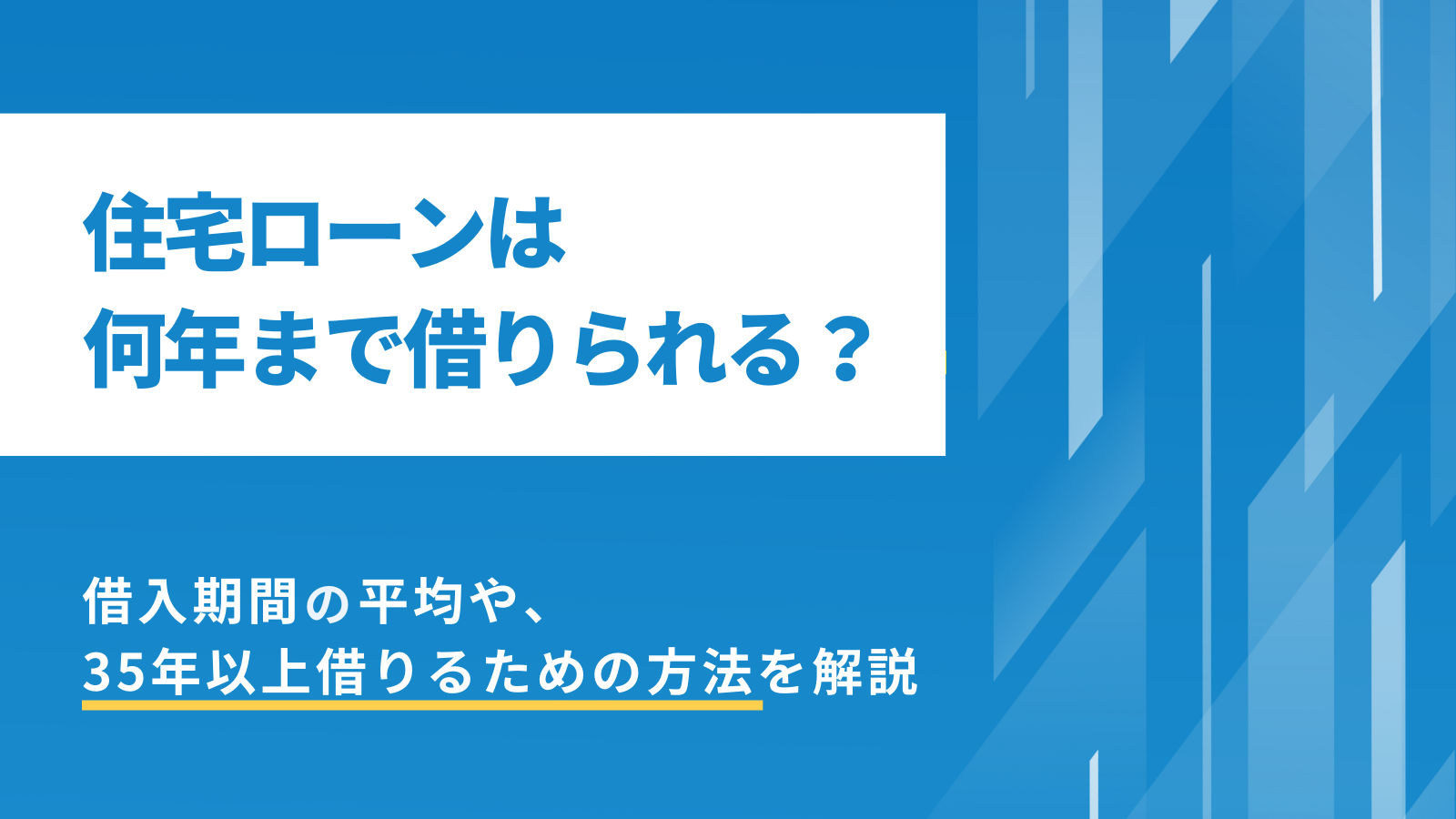-
銀行からのお知らせ
住宅ローンを組む際に、借入期間を何年にすべきか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。住宅ローンの返済は長期にわたるため、今後のライフプランを組む上でも何歳まで返済を続けるかが重要です。
今回の記事では、住宅ローンを組んで住宅を購入した人の平均的な借入期間や、借入期間を決めるポイント、長期で借りるメリットについて解説していきます。
実際に、住信SBIネット銀行が提供している50年の住宅ローンの概要についても詳しく紹介しているため、住宅ローンの借入期間について悩んでいる方は、参考にしてみてください。
目次
住宅ローンの平均借入期間
まずは、住宅ローンの平均的な借入期間について確認しましょう。国土交通省が公表している「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、住宅の種類別の平均借入期間は下記のとおりです。
| 新築 | 注文住宅(建築) | 32.8年 |
|---|---|---|
| 注文住宅(土地) | 34.5年 | |
| 分譲戸建住宅 | 32.7年 | |
| 分譲集合住宅 | 29.7年 | |
| 中古 | 戸建住宅 | 28.4年 |
| 集合住宅 | 28.5年 |
種類別の借入期間をチェックすると、新築住宅の方が中古住宅に比べて平均借入期間が長めに設定されている傾向があります。新築住宅の種類別では「注文住宅」の平均借入期間が最も長く、次いで「分譲戸建て住宅」、「分譲集合住宅」の順となっています。
ただし、上記はあくまで平均値であり、最適な借入期間は人によって異なります。借入期間を決めるときの一つの目安として確認しておきましょう。
住宅ローンの借入期間を決めるためのポイント
住宅ローンの借入期間を決めるにあたっては、いくつか押さえておきたいポイントがあります。特に、「完済時の年齢」「毎月の返済額」「今後のライフイベント」の3つに注目しましょう。
何歳までに完済するか
まずは、今後のライフプランから何歳までに住宅ローンを完済したいかをイメージしましょう。例えば、定年退職までに住宅ローンを完済したいなら、退職予定の年齢から現在の年齢を引くことで、最長の借入期間を計算できます。35歳で住宅ローンを組もうと考えている人が65歳で定年を迎える場合、30年の住宅ローンを組むと定年とほぼ同じタイミングで完済が可能です。
また、ほとんどの金融機関では完済時年齢に上限を設けています。上限年齢は金融機関によって異なりますが、80歳未満とするのが一般的です。この場合、35年の住宅ローンを組もうと思うと44歳が上限となります。45歳以上の方は、年齢に応じて借入可能期間が短くなります。
月々の支払い金額をいくらにするか
住宅ローンの返済は、家計における固定費となるため、月々の返済額をどのくらいに抑えたいかも重要です。
現在の支出と収入を考慮して、毎月住宅ローンの返済に充てられる金額がどの程度かを考えます。賃貸物件に住んでいる方は、現在の家賃を基準にしてどの程度増やすもしくは減らすかを検討しましょう。
無理なく返せるかどうかを判断するためには、返済負担率もポイントとなります。返済負担率とは、年収に占める年間返済額の割合のことです。
返済負担率は、一般的に20%〜25%以内に収めるのが理想的だと言われています。例えば、年収500万円の人が返済負担率を20%に抑えようと思うと、年間の返済額は100万円となります。
借入総額を理想的な年間返済額で割ると、返済を終えるために必要な期間が大まかに計算できます。これを基準に借入期間を決めていくのも一つの手です。
完済までのライフイベントは何があるか
住宅ローンの返済は長期にわたるため、完済までのライフイベントも考慮した上で返済計画を立てることが大事です。子どもの教育費の増加や車や家電の買い替えなど、将来的に想定される費用は前もって考慮しておきましょう。
加えて、住宅購入後は固定資産税や修繕費などの維持費やリフォーム費用などが必要となる場合もあります。住宅購入によって生じる支出も把握しておきましょう。
また、変動金利で住宅ローンを借りる場合は、将来の金利上昇リスクにも注意が必要です。適用金利が上がると、想定よりも返済負担が大きくなるケースもあります。将来の金利動向について正確に予測するのは難しいですが、どこまでの金利上昇なら許容できそうかをイメージしつつ、繰上げ返済や借り換えといった方法も視野に入れておくのをおすすめします。
住宅ローンを長期で借りるメリット
住宅ローンを長期で借りるメリットとしては、「毎月の返済額を抑えられる」、「借入可能額が増えやすい」といった点が挙げられます。詳しく確認していきましょう。
毎月の返済額を抑えられる
住宅ローンを長期で借りると、1回あたりの返済金額が少なくなります。そのため、短期間の住宅ローンに比べて毎月の返済額を抑えやすいという点がメリットです。収入に不安がある場合や、将来に向けて貯蓄に取り組みたい場合などは、なるべく返済額を長期間に設定するのが良いでしょう。
ただし、借入期間が長期化すると、その分支払う利息の金額は増えるため、総返済額も大きくなります。金融機関によっては、借入期間を長くすることで適用金利が上乗せされるケースもあります。毎月の返済額と総返済額のバランスを見つつ、無理なく返せる返済額を決めていきましょう。
借入可能額が増えやすい
住宅ローンの審査では、契約者が安定的に返済を行えるかを総合的に判断した上で、借入可能額を決定します。返済が滞るリスクが低いと判断されれば、借入可能額が増える可能性があります。
借入期間を長期間に設定すると、年間の返済額が小さくなるため、年収に対する返済負担も小さくなります。長期で住宅ローンを申し込むことで、無理なく返済を続けられると判断されやすくなるでしょう。
借入可能額が物件の購入価格に届かない場合は、借入期間を長く設定することで借入可能額が増えるケースもあります。
住宅ローン35年以上借りるための方法
近年、円安や資源価格の高騰の影響を受けて、住宅価格が上昇しています。価格上昇は今後も継続する見込みであるため、これから住宅を購入するのはハードルが高いと感じる方もいるでしょう。
こうした状況を受けて、住信SBIネット銀行では2023年8月より最長50年の住宅ローンの取り扱いを開始しました。ネット銀行としては初の取り組みで、概要は下記のとおりです。
| 対象商品 |
|
|---|---|
| ご利用いただける方 |
次の条件をすべて満たす方
|
| 借入期間 |
【新規】1年以上50年以内 【借換】[35年-借換対象となる住宅ローンの経過期間]を借入期間の上限といたします。なお、当初35年超で借り入れた住宅ローンを借換えする場合は、その住宅ローンの残存期間を上限といたします。 |
| 借入金額 | 500万円以上2億円以下(10万円単位) |
| 金利上乗せ | 借入期間を35年超~50年以内で借りる場合は、住宅ローンの適用金利に年0.15%が上乗せ |
| 金利タイプ |
|
| 団体信用生命保険 | 団体信用生命保険(スゴ団信)(引受保険会社:SBI生命保険株式会社) |
| 事務取扱手数料 | 借入金額の2.2%(税込) |
最長50年での借入が可能なのは、「住宅ローン(WEB申込コース/対面相談コース)」「NEOBANK住宅ローン」です。フラット35およびフラットパッケージローンは対象外となります。
完済時年齢には満80歳未満という上限が設定されているため、最長の50年で借りられるのは満29歳未満の方までです。借入期間が最長35年から50年に延びたことで、20代から30代の若年層にとっては、借入期間を長期化して毎月の返済額を抑えやすくなったと言えるでしょう。
ただし、35年より長く借入を行う場合は、住宅ローンの適用金利に年0.15%が上乗せされます。借入期間が延びることで月々の返済負担は減少しやすくなりますが、適用金利が上がると総返済額は大きくなります。最終的にどのくらいの影響が出るかは、あらかじめシミュレーションツールなどで確認しましょう。
まとめ
住宅ローンの借入期間を長くすると、毎月の返済額が抑えられて、借入可能額も増えやすくなります。ただし、総支払額が増えやすくなる点や、完済時の年齢に注意が必要です。
住宅ローンの借入期間を決める際は、「完済時の年齢」「毎月の返済額」「今後のライフイベント」の3つに注目しつつ、無理なく返済を続けられる計画を立てることをおすすめします。
住宅ローンシミュレーションを利用すると、希望する返済期間によって毎月の返済額や総返済額がどのように変わるか試算できます。事前に返済計画をきちんと立てるためにも、まずは住宅ローンシミュレーションを利用しましょう。